私たちは、どこへ行こうしているのか~終戦から80年~
- kazenooka
- 2025年8月13日
- 読了時間: 3分
更新日:2025年8月15日

就労支援センター風の丘では、コロナ禍以前は、毎年夏になると、茨城県の阿見町にある『予科練平和記念館』に利用者さん、職員全員で行っていた。
「予科練」とは、「海軍飛行予科練習生」またはその制度の略称で、14歳半から17歳までの少年を全国から選抜し、搭乗員として訓練する。
終戦までの15年間で約24万人が入隊し、約2万4千人が飛行練習生課程を経て、戦地へ赴いた。特別攻撃隊(特攻隊)として出撃した者も多く、戦死者は8割の1万9千人にのぼった。
このような歴史的背景を踏まえ、予科練に関する資料を保存・展示するともに、戦史の記録を風化させることなく、次の世代へ継承させるために建設された記念館こそ、この予科練平和記念館にほかならない。
たぶん通算では、もう10回近くは行っていると思う。
いつも前もって案内人となる方を事前にお願いし、ご説明いただきながら館内をめぐるようにしている。
そのときの案内人は、おそらく5、60代と思われる、柔和な表情をした男性であった。
とても詳細なご説明だったことを覚えているが、どちらかというと、淡々とお話されていたと記憶している。しかし、後ほど、この「淡々」は、湧き上がる感情を必死でこらえていたからだということを、思い知らされる。
最後にエントランスでひと通りの説明を終えた後、では…、と言いながら、これまでとやや異なる雰囲気で話し始めた。
その声は、緊張からか、やや震えていた。
“あそこに座っている男性をご覧になって下さい。
あの方は予科練を出て、特攻隊で、生きて帰ってきた方です。
今日は珍しくここに来ています。
彼がよく話していることは、戦地の兵士のうちで、実際に戦闘を経験した兵士のうちで、戦争をしたかった者など誰もいない、ましてや敵兵を殺したいなどと思っていた者など、いるわけがない、ということです。
戦争をし始めるのは、政治家や官僚など、自分が戦地に行って、実際に戦地で闘うことなど想像すらしたことがない人々で、勇ましいことを言っていた人々は、みんなそうだった、と。
じつはあそこに座っている、特攻隊で生きて帰ってきた男性とは、私の父です。
みなさんにお願いがあります。
どうか、愚かな政治家の話に、惑わされないようにしてください。
それが、父と私からのお願いです。”
居並ぶ全員が、息を呑んだ。
まさか、最後の最後に、こんな強烈な話があるとは思ってもいなかった。
改めて、お父様に挨拶に行った。
「栃木県の佐野市から来ました。毎年、記念館に来させていただいています」と挨拶すると、
「ご苦労様です。必ずまた来てください」と深々とお辞儀をされた。
今月の対話会に、講師としてお越しくださる柳澤協二さん(元内閣官房副長官補)は、以前、戦争に肯定的な若者に、自衛隊の生命の危険性などについて話したところ、“だって仕事なんだから仕方ないでしょ”と返答されたという。
衝撃を受けた柳澤さんは、“自分の生命については勇敢であっていいかもしれないが、他人の生命には臆病でなければ、まともな安全保障論議などできるはずがない”と思ったという。
終戦から80年。
私たちは、どこへ行こうしているのだろうか。
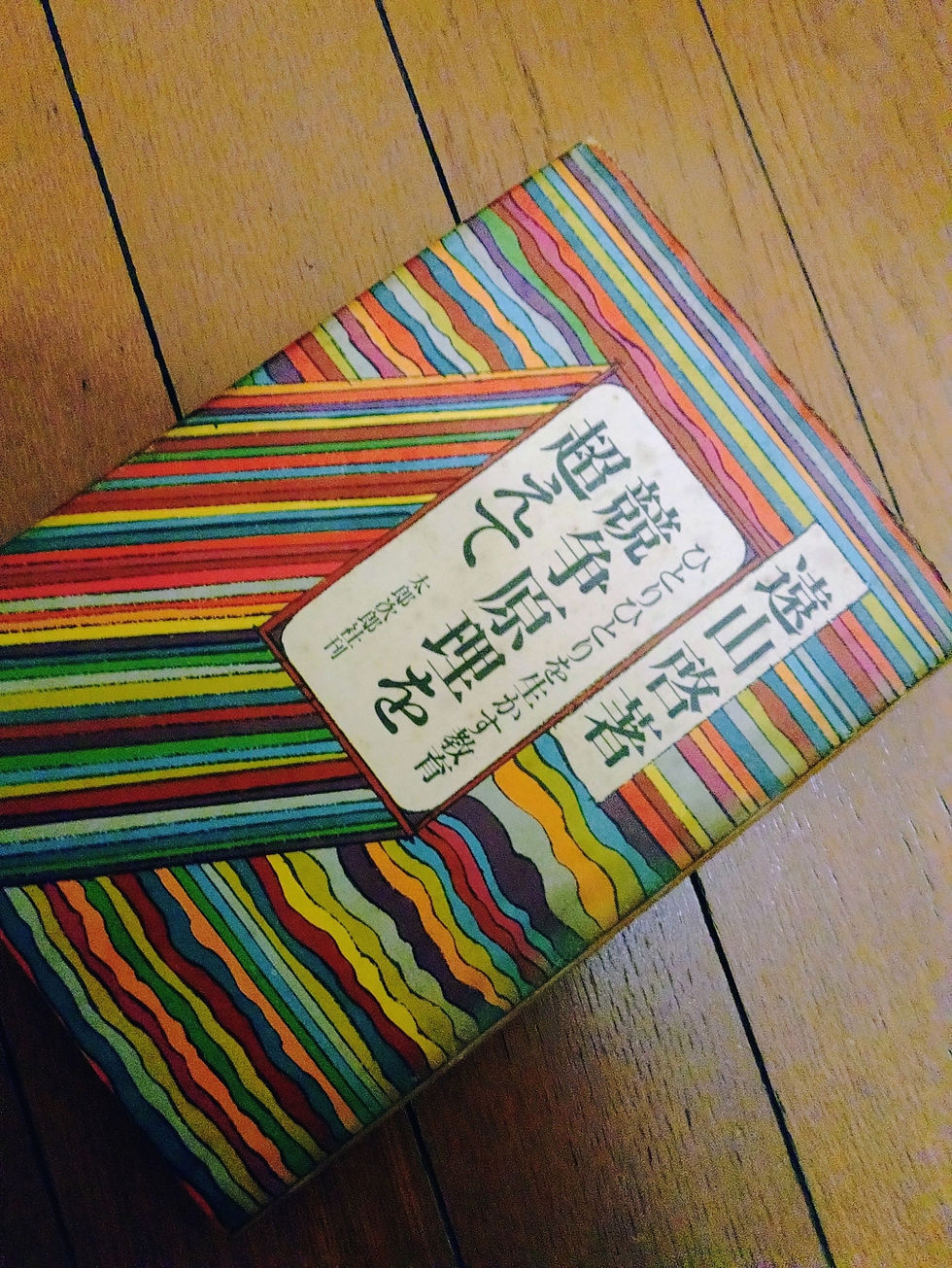


コメント